幼児教育実践学会
第15回幼児教育実践学会 口頭発表 企画趣旨概要一覧
2024年8月24日(土)9:00~10:30/11:00~12:30
口頭発表【Ⅰ】 9:00~10:30
- Ⅰ-1
- 北海道地区:丸谷雄輔(認定こども園札幌ゆたか幼稚園理事長・園長)、長谷部静(認定こども園札幌ゆたか幼稚園学年リーダー・保育教諭)、川端美穂(北海道教育大学教授)
- テーマ:『園内研修の可能性を探る』~私達が大切にしたい実践知の在り方~
- 子どもと織り成す保育実践の中で、偶発的に起っているいろいろな出来事を振り返り、改めて意味を掘り返していくといった語り合いが、保育を豊かにしていく営みの土台となっていることを実感している。また、多種多様な園内研修をデザインすることによって、重層的な学びの土壌が保障され、保育者としての専門性を高める園文化として醸成されてきている。一方で学びの価値は目に見えにくく、どのような保育場面において生かされているのかは不透明な部分が多いため、学び合いの風土が実践の場に与える可能性を探ると共に、実践共同体の知としてどのように寄与しうるのかについてあらためて問い直してみたい。
- Ⅰ-2
- 神奈川地区:森本壽子(鎌倉女子大学幼稚部部長)、山崎和子(ひだまりの保育園園長)山﨑舞(ひだまりの保育園保育教諭)、沖永なつみ(宮前幼稚園年長学年主任・教諭)、佐伯胖(東京大学名誉教授)
- テーマ:一人ひとりを、心から大切にする保育とは。
- 保育園や幼稚園に通う園児たちは、仲間と一緒の生活の中でも自分らしさを発揮しながら一日一日を、精一杯生きようとしている。しかし、保育者達は、その子の良さをしっかりと受け止めながら、集団生活の中であってもその子がどれだけ自分を発揮してのびのびと幸せな生活を送れるようにしているだろうか。改めて、保育者の関わり方を事例を通して見つめなおす機会としていきたい。
- Ⅰ-3
- 九州地区(長崎県):谷川慶子(東大野幼稚園園長)、山内咲耶(東大野幼稚園教諭)、山口結依子(東大野幼稚園事務員)、中尾健一郎(長崎短期大学教授)
- テーマ:自然体験を通して、心豊かにたくましく生きる力を育む~「10の姿」をもとに子どもの成長を捉えながら~
- 本園で行っている自然体験や山登りでは、子どもたちの興味・関心を刺激し園生活で獲得できない多くの経験や体験ができると考えている。具体的には子どもたちが遊び込める要素が多く、心の変容や体の使い方などの成長が顕著で、個人だけでなく子どもたち同士の協働性や思いやりなど関わりが深くなる姿が見られるからである。そこで本研究では、自然体験に取り組む子どもたちのエピソードを記録し、体験後の子どもたちの心や体の変化も聞き取りながら、その実態を明らかにし、幼児期に育ってほしい10の姿をもとに子どもの成長を捉え、自然体験や山登り体験の効果について検討する。
- Ⅰ-4
- 大阪地区:中島美和子(パドマ幼稚園総主任・研究主任)、岡田尚子(パドマ幼稚園学務主任)、弘田みな子(神戸教育短期大学講師)
- テーマ:「設定保育」再考~「こどもがまんなか」の設定とは~
- 現在、本園では、子どもと保育者が共に主体的である保育を目指す取り組みの過程にある。保育者の願いから設定されてきた「設定保育」とは何かについて改めて見直し、子ども達が自分達の活動を計画し、参画出来る「設定保育」の取り組みを模索している。その中で見えてきた、保育者と子どもと保育カリキュラムの関係性や、子ども参画の在り方について、運動サーキット遊びや防災訓練の取り組みなどに関する実践報告を交えて考察していく。
- Ⅰ-5
- 四国地区(香川県):港麻里栄(ときわ幼稚園主任)、津川美絵(ときわ幼稚園教諭)、山神眞一(香川大学副学長)
- テーマ:子どもと共にあゆむ保育~非認知能力の育成を通して~
- 保育目標を「豊かな心とたくましい体をもった子」と定め、園庭が広く豊かな環境の中で全園児が活発に遊び、交流も盛んである。子どもたちどうしが楽しく関わり合う姿や保育者とともに遊びを高める姿がみられる。このような中で「非認知能力」で育まれる「コミュニケーション力」「セルフコントロール力」「チャレンジ力」などの内面の力をより高め、子どもの主体性に結び付く教育・保育実践をめざし研究テーマを設定した。
- Ⅰ-6
- 佐賀県:村岡直子(佐賀女子短期大学付属ふたばこども園副園長)、田島大輔(和洋女子大学助教)
- テーマ:園内研修のあり方 園内研修(共に育つ)を通して見えてきた保育現場での変容と今後の課題
- 本園では園内研修を1年間で約40回企画している。①基本研修として外部講師からの講話の傾聴②研究保育を実施し、ドキュメンテーション研修の手法で振り返り③遊びを主体とした保育を目指す他園との交流研修④県内新採保育者向け公開保育・ECEQ®公開保育⑤1年間の研修を終えてのポスター作成など多様な研修を実施している。研修を通して保育が良い方向に変容したと実感することがある。今後、常に長時間の保育を担保しつつ更なる質の向上のためにどのような研修がいいのか検証したい。
- Ⅰ-7
- 北海道:照井悠斗(幼保連携型認定こども園おかだまのもり年長組リーダー)、井上優美(幼保連携型認定こども園おかだまのもり2歳児リーダー)、谷島直樹(九州大谷短期大学客員教授/幼保連携型認定こども園おかだまのもり園長)
- テーマ:ラーニングストーリーによる保育者、保護者、子どもを繋ぐ記録の考察~保育者と保護者の視点変革:子どもが力を発揮する環境を創造する~
- 子ども個人に焦点を当てた保育記録の方法を再検討し、ラーニングストーリーという子どもの学習経験や成長を物語性のある形式で記録し、今後の支援を検討する方法を採用した。この記録は保育者、保護者、子どもで共有する事も目的とされ、ラーニングストーリーを通して保育者と保護者の視点を変革し、子どもが力を最大限に発揮できる環境を創出するための肯定的な瞬間を捉えて共有するものである。この変化が保育の質の向上と子どもの成長にどう影響するかを探求したい。
- Ⅰ-8
- 兵庫県:濱名浩(認定こども園立花愛の園幼稚園理事長・園長)、森陽一(認定こども園立花愛の園幼稚園副園長)、荒木真美(認定こども園立花愛の園幼稚園学年主任)、高橋健介(東洋大学准教授)
- テーマ:「劇遊びでの子どもと保育者の共主体について」
- 5歳児の発表会(劇遊び)に向けて子ども達が主体的に取り組み、保育者と子ども達の対話を通じて、より深く登場人物の気持ちや思いに気づき、理解と表現を深めていく保育者の働きかけとは何かについて発表する。また、劇遊びの取り組みを動画で撮影し分析する中で、子ども達の主体性の発揮とは何か?保育者の主体性とのバランス(共主体)についても考察する。
- Ⅰ-9
- 大阪府:安家匠(あけぼの幼稚園園長)、渡辺聖也(あけぼの幼稚園副主任)、前原沙耶香(あけぼの幼稚園教諭)、安家周一(梅花大学教授)
- テーマ:異年齢保育の可能性
- 日本の教育、保育では当たり前のように学年割りで学級を編成することが多い。世界に目を向けてみると年齢にとらわれない進級・入学制度をとっている国もある。育ちの幅が広い子ども達にとって同学年の教育、保育がいいのだろうか。自園では年中クラスで2年過ごした例、就学猶予制度を利用して年長クラスで2年過ごしたのちに小学校に入学した例がある。その事例も踏まえて、異年齢の子ども達が多くの時間を共にする学級編成の可能性を考えたい。
- Ⅰ-10
- ECEQ®・評価チーム:藪淳一(ECEQ®・評価チーム長)、天野美和子(東海大学講師)、矢崎桂一郎(国立教育政策研究所幼児教育研究センター研究員)、淀川裕美(千葉大学准教授)
- テーマ:ECEQ®と幼児教育の質評価
- 令和元年度・2年度文部科学省委託「幼児教育の教育課題に対応した指導方法等充実調査研究」実施にあたり、東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター(Cedep)と共に当機構ECEQ®・評価チームが共同研究した「ECEQ®の質的検証」についてその成果を発表し、当機構が目指す幼児教育の質評価について迫りたい。
(共同研究者(Cedep))野澤祥子(東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター准教授)
口頭発表【Ⅱ】 11:00~12:30
- Ⅱ-1
- 東京地区:田澤里喜(東一の江こども園園長)、関岡貴之(多摩みゆき幼稚園園長)、井上眞理子(洗足こども短期大学教授)
- テーマ:保育の質向上を目指す「保育マネジメント」の実践と課題〜各園のマネジメント実践を高める研修の取り組み〜
- 保育の質向上を目指す上で園のマネジメントの意識と実践は重要であり、また、これに対する園長の役割は非常に大きい。これらの意識や役割の充実及び各園におけるマネジメント実践のあり方を検討するため、東京都私立幼稚園連合会教育研究委員(園長)を対象に参加希望を募り、希望各園が目標設定をしたマネジメントをそれぞれで実践し、持ち寄り往還的に研修をすることとし、各園の「保育マネジメント」の充実及びそれを支援する研修などについて検討する。
- Ⅱ-2
- 東海北陸地区(富山県):波岡千穂(堀川幼稚園副園長)、藤島秀恵(リンデ幼稚園園長)、千々石寿史(あおい幼稚園主幹保育教諭)、原田由美(認定こども園いずみ幼稚園教頭)、岡健(大妻女子大学教授)
- テーマ:ECEQ®公開保育の普及と理解に繋がる「富山型ミドルリーダー育成研修システム」
- 本研究では、ECEQ®公開保育の普及と理解を深めるためのミドルリーダー育成研修の取り組みについて報告する。「富山型ミドルリーダー育成研修システム」は、(一社)富山県私立幼稚園・認定こども園協会加盟園全園からミドルリーダーを集め、彼らの能力向上を目指して開発された研修システムである。このシステムは以下の3つの柱で構成されている。①保育の多様な分野の知識を深めるための分野別研修②講義や演習、自園での実践を通じてファシリテーションスキルを高めるファシリテーション研修③ECEQ®公開保育への参加。これらの研修を受けた受講者は、各園でリーダーシップを発揮し、園内研修の推進を通じて保育の質をさらに向上させることが期待される。実施から4年目を迎えた現在、これまでの取り組みから明らかになった成果と新たな課題について考えていきたい。
- Ⅱ-3
- 関東地区(茨城県):木村直文(認定こども園石岡幼稚園園長)、島田友美(認定こども園石岡幼稚園教諭)、加藤松江(認定こども園石岡幼稚園教諭)、田中栄一(アイティソルブ株式会社教え方研究所代表)、菊地一晴(聖徳大学専任講師)
- テーマ:幼児期における「英語発音あそび」を通しての活動について
- 英語の発音に特化した「英語発音あそび」を導入して11年となる。先生方が実際に一緒に発音する事で、楽しみながらしっかりとした発音が出来る事を願って日々活動を継続している。その継続活動での経緯や幼児期における英語指導の一つとして発表したいと考えている。
- Ⅱ-4
- 近畿地区(和歌山県):松下瑞良(認定こども園湯浅幼稚園園長)、中川摩耶(認定こども園湯浅幼稚園保育教諭)、土橋紀香(認定こども園湯浅幼稚園保育教諭)、上田美奈子(認定こども園湯浅幼稚園副園長)、安達譲(大阪教育大学非常勤講師/せんりひじり幼稚園園長)
- テーマ:「主体的な子どもの育成をめざして」~サークルタイムはじめました~
- これからの予測困難な時代を生きていく子どもたちに、目の前の答えのない課題に対して、自分たちで主体的に考え話し合って納得解や最適解を生み出していって欲しいと願い、サークルタイムを取り入れているが、「うん、それでいい」「なんでもいいよ」と言う子どもの姿や、全く自分の意見を譲らない子どもの姿があり、保育者がどこまで介入すればよいのか悩む日々である。話し合いから合意形成に至る過程や活動を通して、子どもたちにどのような力が育っているのか、又保育の中で大切にしていきたいことを、事例と共に考えていきたい。
- Ⅱ-5
- 中国地区(島根県):森脇尚子(松江暁の星幼稚園園長)、上代菜月(松江暁の星幼稚園教諭)、西知恵(松江暁の星幼稚園教諭)、松尾奈美(島根大学講師)
- テーマ:「互いに学び合う、縦割りクラスでの一人ひとりの育ち」
- 縦割り保育ならではの異年齢同士の生活の中では、年上の子が年下の子を慈しみ、年下の子は年上の子への憧れや尊敬が自然と生まれている。そのような園生活の中で子ども達が互いに教え合い、学び合っている姿をよく見かける。これらのことから一人ひとりの子ども達の可能性がどのように引き出され、お互いの学びとなっているのか。そして教師がそれをどう受け止め、援助していくかを考え、どのように保育に生かしていくか職員間で話し合いを進めている。
- Ⅱ-6
- 兵庫県:西村亜実(認定こども園七松幼稚園主幹保育教諭)、岩野志保(認定こども園七松幼稚園保育教諭)、白野未侑(認定こども園七松幼稚園保育教諭)、亀山秀郎(OCC教育テック総合研究所上席研究員)
- テーマ:ミドルリーダーが考える園の地域における役割・使命とは
- クラスの活動の中で地域との連携という部分に意識を向けて保育を行ってきた。更に地域との連携を深めていくために、七松学園のリーダーが集まり、地域とどのように歩んでいきたいか、また地域にどのような発信をしていくのかを、近い未来を見据えて考えた。今回の発表では、これまでの話し合いの過程と、本園の強みを生かした地域との関わり方について発表する。また地域の中における園のあり方について、参加者と共にグループワークを行う予定である。
- Ⅱ-7
- 北海道:司馬政一(幼保連携型認定こども園せいめいのもり園長)、柳田未那美(幼保連携型認定こども園せいめいのもり教諭)、佐藤瑞姫(幼保連携型認定こども園せいめいのもり教諭)、田中住幸(札幌大谷大学短期大学部学科長・准教授)
- テーマ:子どもと一緒に考える保育とは
- 子ども主体の保育を進めていくと、子どものために大人が仕掛けるだけではなく、子どもと考えながら日々の暮らしを創っていくところに保育の醍醐味を感じるようになった。本質的に子どもが育つ保育のあり方について、保育者の思考の変化やそもそも生きるとは何なのか?を追求し、その実践の変遷について皆さんと考える場としたい。そして、保育者自身が心解放され、活力ある職場の中で実践していける答えを模索したい。
- Ⅱ-8
- 埼玉県:佐久間百恵(大宮みどりが丘幼稚園教諭)、三浦悠衣(大宮みどりが丘幼稚園教諭)、大澤洋美(東京成徳短期大学教授)
- テーマ:学びをつなぐ~ダンボールを使った遊びをみつめて~
- 4歳児クラスでは、自分の好きな遊びをみつけて、そこから友達と一緒に遊ぶ楽しさを味わい成長して欲しいと願っている。今回の発表では、4歳児の4月からの遊びの環境に焦点をあて、遊びの中の人間関係や遊び込む為に必要な援助についてみつめ、3歳児からの学びのつながりについて、考察していく。フロアーの皆様に遊び込む為の環境作りについて伺い学びを深めていきたい。
- Ⅱ-9
- 大阪府:岩﨑巧(森のあそびば はれのちはれ代表/桃山学院教育大学非常勤講師)、三倉敏浩(豊中あけぼのこども園園長)、藤田勲(あけぼのぽんぽここども園園長)、湯浅優典(せんりひじり幼稚園年長学年主任)
- テーマ:『園』の『庭』で心が揺さ『振』られる『幅』~世界はそれを「好奇心」と呼ぶんだぜ~
- 昨年度の口頭発表にて、園庭にはなるべく原始的な要素(Society1.0)が必要であり、デジタル(Society4.0)が溢れる家庭との「経験値の振幅」を生む事が大切であるという仮説に至った。今回3法人4園の園庭で遊ぶ子どもの姿を分析し、家庭環境や保育時間の違いによるSocietyの「幅」と「量」の関係性を検証した。予測不能な社会(Society5.0)を生きる子ども達の為に日々“ワクワク”する園庭作りに挑まれている全国の園に本合同研究の内容を寄与していきたい。
- Ⅱ-10
- 北海道:立田祐理(恵庭幼稚園指導教諭)、渡邉日向子(恵庭幼稚園年長組主任・教諭)、藤澤侑香(恵庭幼稚園教諭)、井内聖(北海道文教大学客員教授)
- テーマ:個と集団のバランスから考える自律した子どもを目指す幼児教育
- 予測不可能な未来を健やかに生き抜いていくためには、自分の個性や得意なことを活かし、自ら楽しみを見つけ、自分の力で道を切り拓いていく力が必要だと考える。しかし、その力だけでは集団として力を発揮することができない。私達が日頃のクラス・学年運営で感じる「集団としてまとまってきた」の感覚は、どのような要因や保育者の視点が影響を与え、形作られているのだろうか?自園が教育の果てに目指す子どもの「自律した姿」を、個と集団の両者の観点からどのように構成され評価すべきかを整理し、論じていきたい。






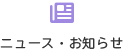
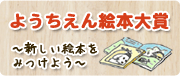
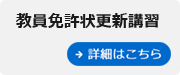
 ページ上部に戻る
ページ上部に戻る お問い合わせ
お問い合わせ
